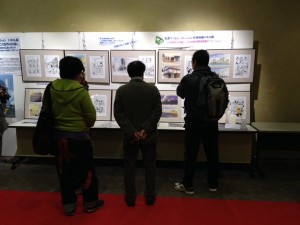広島国際映画祭レポート
2015.12.04
皆さん、こんにちは。
『この世界の片隅に』制作宣伝担当の山本です。
私は、7月の「制作支援メンバーズミーティング」と10月の「練馬アニメカーニバル2015」における『この世界の片隅に』トークイベントで、司会進行を担当させていただきました。どの会場でも皆さんの温かい応援に支えられてきました。本当にありがとうございます。この場を借りて御礼申し上げます。
さて今回は、去る11月23日に「広島国際映画祭」にて開催された片渕須直監督によるワークショップ《『この世界の片隅に』のさらなる進展。 ―― 昭和10年の江波・草津、昭和19年の呉――》の様子をレポートします。
あ、すみません、今回は画像少なめ、文章長めです。ゆっくりお読みいただければ嬉しいです。
***
「広島国際映画祭」は2009年より「ダマー映画祭inヒロシマ」として開催されてきましたが、昨年より「広島国際映画祭」となりました。よって今年は「第2回広島国際映画祭」です。片渕須直監督による「この世界の片隅に」のワークショップは、2012年の「ダマー映画祭inヒロシマ」から開催されており、今年で4回目となります。
11月23日当日は、前日までの雨予報が見事に外れ、快晴。
会場は広島県庁の真向かいにある「基町クレド」という複合商業施設の11階にある「NTTクレドホール」です。ホールフロア全体が「広島国際映画祭」の会場ですが、そのラウンジ部分を第2会場とし、ここで「この世界の片隅に」のワークショップが開かれました。
9時30分からという早い時間にもかかわらず、会場はほぼ満員。一般のお客様に交じり、《「この世界の片隅に」を応援する呉・広島の会》代表の大年健二さんや、ヒロシマフィールドワークの中川幹朗先生のお顔も見えます。またMAPPAの丸山正雄プロデューサーも急遽駆けつけ、会場後方の椅子にさりげなく座っています。
そんななか、広島フィルムコミッションの 西崎智子さんが片渕監督を呼び込むと、大きな拍手が沸き起こりました。
実は片渕監督は、11月20日から那須で行われた「アニメーションブートキャンプ」の講師を務め、22日に浜松に移動して「はままつ映画祭」での『この星の上に』上映とトークショーに参加、その夜広島に移動した翌朝がワークショップという超強行軍での参加。
(MAPPA公式サイト http://www.mappa.co.jp/ に片渕監督が連載しているコラム「すずさんの日々とともに」第27回もあわせてお読みいただけると、さらによくわかると思います)
その疲れも見せずに、片渕監督は話し始めます。
まず、片渕監督が監督として手掛けた劇場作品2本の紹介から。
1本目は2001年公開の『アリーテ姫』。
中世ヨーロッパを舞台としたファンタジーのように見せつつ、実はSF的要素も盛り込んだ作品。中世ヨーロッパの雰囲気を出すために、様々な資料をあたって架空の中世の街を描き出したとのこと。2002年にパリで上映された際、映画の舞台がフランスであるとは語られてないにもかかわらず、現地の観客から「なぜフランスを舞台にした映画を創ったのか」と尋ねられたそうです。中世ヨーロッパの街を再現するために参考にした資料の多くがフランスのものだったかもしれないと述懐する監督。描かれた風景が、見る者に場所と年代を感じさせることを改めて強く認識されたそうです。
では、それを自国・日本を舞台にしたらどうなるか。そう考えている時に、当時のマッドハウス社長・丸田順吾さんから持ち掛けられたのが、直木賞作家・髙樹のぶ子さんの自伝的小説『マイマイ新子』だったといいます。同作の舞台は昭和30年の山口県防府市。片渕監督には全くゆかりのない土地です。そこで監督は、何度も現地取材に赴き、また古地図や写真を集め、当時の街並みがどのようであったかを調べ尽くそうとしました。その現地取材の中で偶然出会ったのが、平安時代の屋敷跡の発掘調査現場です。庶民の家とは明らかに異なる屋敷の広大さに興味を持った監督は、周防国の国府だったこの場所に一体誰が住んでいたのか調べます。その結果、国司として派遣されていた貴族・清原元輔の存在が明らかになりました。清原元輔とは誰あろう、あの清少納言の父にあたる人物。つまり、8歳の清少納言が、この防府の地に住んでいたのです!約50年前の山口県防府と1,000年前の周防国が劇的につながり、映画はその2つの時代の少女たちを描く形で完成しました。それが2009年公開の映画『マイマイ新子と千年の魔法』というわけです。
『マイマイ新子と千年の魔法』には新子のお母さんが登場します。どこかのほほんしていてマイペースな彼女は作中、雑誌の読者モデル募集の企画に応募して入選してしまうような人物。彼女が終戦前に生まれていることに、片渕監督は気づきます。私たちは戦争中のことを考えるとき、歯を食いしばって必死に生きている姿しか思い浮かべることができないでいますが、新子のお母さんのようにのほほんとした感覚を失わずに生きていた人もいるのではないか。そう思い始めた片渕監督が出会ったのが、こうの史代さんのマンガ『この世界の片隅に』でした。
ここまで話し終わったところで、『この世界の片隅に』の物語冒頭部分にあたる「冬の記憶」が上映されました。
内容は、江波に住むすずさんが、兄の代わりに海苔を届けに広島中心部に行くもの。その中には、今では原爆によって失われてしまった町・中島本町が登場します。川を遡っていくすずさんを追うカメラは中島本町の全景を雄大に映し出し、現在は平和記念公園のレストハウスになっている「大正屋呉服店」前に人が行き交う賑やかな様子も繊細に描き出します。
現地の綿密な調査に加え、当時を知る方々にもお話を伺い、物語のバックボーンとなる当時の「風景」がいかなるものだったかを、可能な限り再現しようとした監督とスタッフたちの生んだ渾身の映像。
上映が終わると満員の会場から拍手が起きました。
その後、映像を見ながら監督が解説を加える「生コメンタリー」状態でもう一回上映されました。
「冬の記憶」の中で特に印象的だったのは、すずさんが船を下りてから、風呂敷を背中に背負って階段を上り出す場面。原作マンガは3コマですずさんの動作が描かれていますが、アニメーションでは一連の動作として見せるため、その間の動きを埋める必要があります。つまり、一連の動作にどれくらいの時間をかけたらすずさんらしいのかを考える必要があるのです。言われてみれば当然ですが、動きそのものだけではなく、動きの速度感も作っていかなければなりません。
ここで、監督が面白い画像を見せてくれました。この場面の作画を1枚に重ねた画像です。ほぼ同じ場所に重なっていて真っ黒になっているのですが、「一連のアクションが大きく跳ねるのではなく、細かい動作を重ねていることがわかる画像です。細かい動作をすることで、見る者が《リアル》だと感じるのです」と片渕監督。会場からは納得のため息が漏れていました。
その後、「パイロットフィルム」を上映。こちらも要所を確認しながら監督が解説を加えていきます。
終盤の重巡洋艦「青葉」が着底するすぐ横岸の広場で、縄跳びをする子供たちが出てきます。そこで監督がボソッと一言、「縄跳び歌がわからん」。場内は爆笑に包まれました。
さらに、監督はいくつかの場面について説明してくれました。
広島電鉄から国鉄に乗り換えるすずさん一行を描くため、国鉄横川駅を描きたかったが、どうしても資料が手に入らず、移動途上にある横川新橋を一行をのせた広電の電車が行くカットにしたこと。国鉄呉線の車窓から見える海の上を行く船「こがね丸」は元遊覧船であったが、この当時は海軍に徴傭されたことなど、映画ではほんの一瞬で過ぎ行く「風景」についても徹底して調べたことに改めて唸らされる解説でした。
そしていよいよ、この「広島国際映画祭」で初お目見えとなる「大潮の頃」の上映。これは「冬の記憶」に続く、冒頭2番目のエピソードです。
「冬の記憶」と同様、無音・字幕付きの上映でしたが、会場中が真剣に見入っていました。
こうして、「広島国際映画祭」での片渕監督のワークショップは終了。
広島フィルムコミッションの西崎さんは、広島に住む者として、失われた街並みがこのように活き活きと蘇ったことは本当に嬉しいと語り、公開に向けて応援を続けていくと改めて決意表明され、会を締めくくりました。
ワークショップ終了後、関連展示のあるスペースに移動して、お客様や関係者との交流を持った片渕監督。
江波の料亭・山文に勤めていたという93歳のご婦人を紹介され、彼女が語る当時の様子に聞き入る場面もありました。すずさんは今年90歳なので、3年先輩の彼女は、学校ですずさんとすれ違っていたかもしれません。
とにかく調べ抜いてリアルに固めることで、すずさんをリアルな存在として感じたいと語った監督。そんな監督は、アニメーション制作が本格稼働している現在、こんなふうにも感じているようです。
「動きが出来上がる、というのが幸せなんだなあ。調べ物なんて所詮その前段に過ぎない。」
(片渕監督のツイッターより)
****
長文にお付き合いくださりありがとうございました。
以上で「広島国際映画祭」ワークショップ《『この世界の片隅に』のさらなる進展。 ―― 昭和10年の江波・草津、昭和19年の呉――》のレポートを終了します。