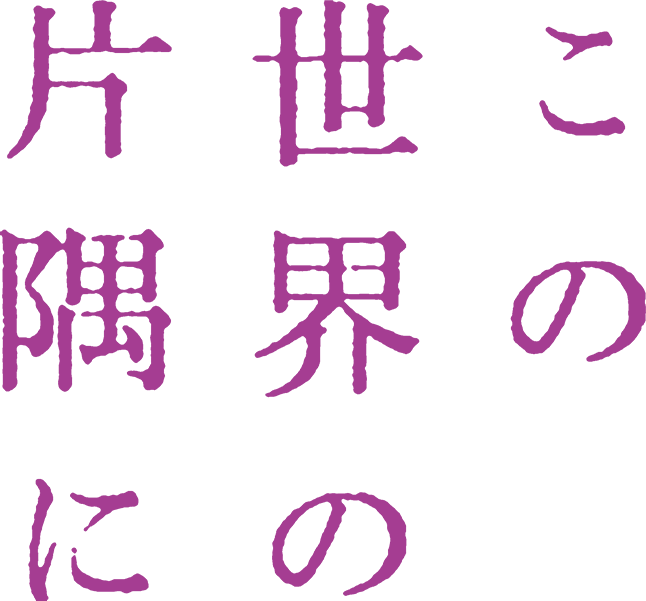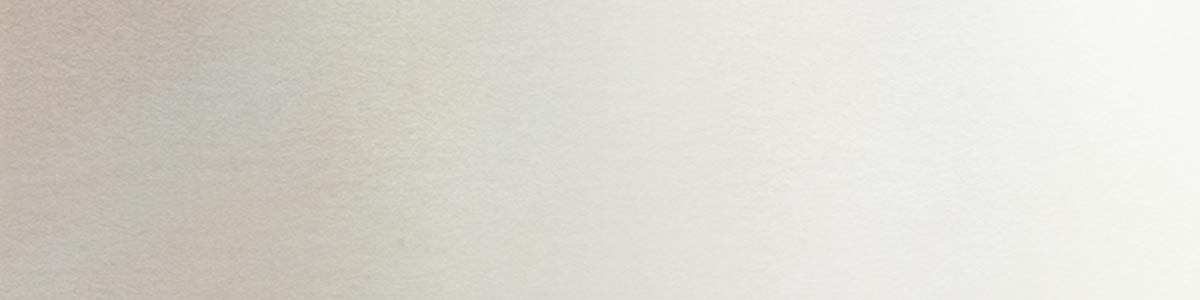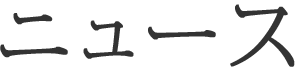2025.09.02
『この世界の片隅に』が伝える“正確に描く意志”──終戦80年リバイバル上映 片渕須直監督ファイナルトークショーレポート

8月28日、テアトル新宿にて映画『この世界の片隅に』リバイバル上映のファイナルトークイベントが開催されました。8月1日から始まった再上映は、終戦80年という節目に合わせ全国で展開され、約1か月にわたり多くの観客の皆さんに支えられてきました。
この日で20回目となるイベントを迎え、会場は満席に。温かな空気に包まれた劇場には、初めてスクリーンで本作を体験する方から、何度も足を運ばれた方まで幅広い観客の皆さんが集いました。
片渕須直監督は冒頭、「8月1日からの上映が、本当に充実した4週間になりました。こうして皆さんと最後の時間を共にできて光栄です」と挨拶。その言葉に、会場からは大きな拍手が送られました。
監督は全国での舞台挨拶やサイン会で寄せられた声を紹介。
「9年前は子どもが小さくて来られなかったけれど、今回は親子で来られた」「幼かったお子さんが成長して、一緒に観られるようになった」という体験談を受け、「80年前の出来事を描いた映画が、今を生きる人々の生活と結びつき、未来へと受け継がれていくことを実感できた」と語りました。
さらに、2016年公開当時に映画評論家・佐藤忠男氏が寄せた評論を紹介。
佐藤氏は終戦時に14歳で地方都市に暮らしていた体験者であり、その視点から本作について「これは基本的にリアリズムの道を歩む進む美術作品で、太平洋戦争末期の日本人の生活を正確に克明に描こうという意思で一貫している。そこには殆ど、これを記憶として後世にまで伝えたい、そういう価値のあるものにしたい、という意志がくっきり感じ取れる。」と評しました。
監督は「実際に戦争を体験された世代から“正確に描かれている”と評価いただけたことは、かけがえのない証明でありありがたいことでした」と振り返りました。そして「こうの史代さんは原作を描くにあたり“自分は戦争を知らないから、一から勉強し直した”とおっしゃっていて、その誠実な姿勢がこうした評価につながったのだと思います」とも付け加えました。
佐藤氏は評論の中で「当時、人々はなぜあれほどまでにおとなしく従順であり得たのか」という疑問を投げかけています。そして、「皆じつに素直で、疑うことなく戦争にも順応していたものである。(中略)何の疑問もなく、と言うよりは疑問の持ち方を知らず、(中略)あの何も考えることのない、何を考えたら良いのかも分からない。考えるべきことの手がかりさえ見当たらない日々としての、あの時代の我々の頭の空っぽさを、この映画ではまざまざと思い出すことが出来る。」と評しました。
片渕監督はこの言葉を受け止めつつ、「すずさんの“ぼーっとしとる”という言葉は、単なる夢想ではなく、時代そのものが抱えていた従順さみたいなもの、しいて言うとするなら至らなさみたいなところを表しているんです。英語字幕で“デイドリーマー(夢想家)”と訳されることが多々ありましたが、それは違うんですと、私は繰り返し伝えてきました」と思いを伝えました。
さらに監督は、声優・のんさんへの演出エピソードを披露。
「最初のマイクテストの際に、すずさんをどう演じればいいかと質問されました。そのとき私は“すずさんは2階建ての人物”だと説明しました。表に見える“1階”のすずさんはぼーっとした日常を生きていますが、その下の“地下”には本当のすずさんがいて、彼女の右手を失う頃から徐々に姿を現してくる。そう演じてほしいとお願いしました」と語り、会場は静かに聞き入っていました。
こうした評論と監督の言葉、そして演技の裏側が重なり合うことで、本作が「時代を正確に描き、未来に伝える意志を持った作品」であることが改めて会場に深く刻まれました。
最後に、監督は「この映画は自分たちの意図を超えて、未来に残っていくべき作品になったと感じました。終戦80年上映としては一区切りを迎えますが、9月以降も全国各地で上映が続いていきます。ぜひ身近な方に薦めていただき、また劇場でお会いできれば幸せです」と締めくくりました。